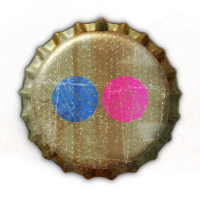作/林真理子
出版社/角川書店(角川文庫)
ReviewWriteDate:2000/8/8
LastUpdate:2000/8/8
Notes:
女子、必読。(笑)
林真理子の有名エッセイ・・・としか書きようがない。
まえがきにある『とにかく私は言葉のプロレスラーになって、いままでのキレイキレイエッセイをぶっこわしちゃおうと決心をかためちゃったのである。』ですべてが言い尽くされてしまうでしょう。
ヒトコトReview:
--------------------------------------------------------------------------------
勝手に自己同一化しちゃいそうなおもしろさ、わたしこそが林真理子
--------------------------------------------------------------------------------
■エッセイスト林真理子、初体験
実は、このエッセイが林真理子初エッセイなのです──わたしにとって。
今まで読んだ林真理子作品というのもちょっと偏っていて『ミカドの淑女』だの『本を読む女』だの
ちょっと時代がかったまじめバージョン。
(『本を読む女』は切ないです。他力本願な本を読む女・・・あたしのことだ)
これが本領じゃないことは知っていながら
踏み込んだら帰ってこれないじゃないかという不安を呼ぶ刊行数。
そんなこんなで世間であれほど有名な作家でありながら、なかなか手が出なかったわけです。
今回はすみません、古本屋で手に入れました。
しばらく部屋のオブジェとなってから順番がめぐってきてさあ読書──
あ、という間でした。解説の通り。
■林真理子化現象
わたしはテレビをあまり見ない人だからなのか?
実は林真理子が色々騒がれているらしいことは知っていてもよくわかっていなかった。
なんでこの人が結婚するってだけでワイドショーなんだ?
と、実は思っていた。
なるほど。こーゆう理由があったのね。(何をいまさら・・・)
内容を読んでいても、このエッセイ、かなり古いことがわかる。
奥付見て・・・初版が昭和60年。
文庫になる前に単行本だったのだろうから、実際の刊行年代は少し前でしょう。
ということはわたしは**才・・・。
これ、そんな昔に「アリ」なんでしょうか、という本音本ですよね。
(本音かどうかはわからないですけど。
上手に手のひらで躍らさせられているのかも。そんな力でみなぎっている。
この場合の踊りは喜んで踊っちゃうけど。)
林真理子はこの中で自分のことを
「自分はナルシストだ」て言いきれる。
一番おもしろいのが『林真理子はなぜ林真理子か』ですよ。
言いきっちゃってでもわたし本当はかわいい女なのよーって必死で言ってみたり
でもどっかでするりとなんか「わかっちゃってたり」する。
えらいのは、というか頭いいのは、
あたしはこんなすごいのよっ、こんな女なのよって言いながら
自分の「世間一般の杓子定規からいけば変なところ、落ちこぼれなところ」ていうのを
ふんだんにスパイスきかせちゃうから、
読んでる側がついつい味方になってしまうところ。
すっかり、同化させていただきました。
わたしこそ、林真理子って。
ふつう、ある程度人っていうものは
「わたしは普通じゃない」
と思っているはず。
どこか特殊でどこか特別で──
そういった心をみごとにくすぐるわけです。
なんだ同じジャン──同じなわけないだろ、て林真理子は笑っていると思いますけど。
こーんな変だけどこーんなモテないけど(笑)でもあたしすごいのよ、って、そりゃすごい。
でもこれって多分コピーライター時代の作品なんだよね?
すでに小説の芽があるんですよね。
他の林小説、いってみようかなあ。
出版社/角川書店(角川文庫)
ReviewWriteDate:2000/8/8
LastUpdate:2000/8/8
Notes:
女子、必読。(笑)
林真理子の有名エッセイ・・・としか書きようがない。
まえがきにある『とにかく私は言葉のプロレスラーになって、いままでのキレイキレイエッセイをぶっこわしちゃおうと決心をかためちゃったのである。』ですべてが言い尽くされてしまうでしょう。
ヒトコトReview:
--------------------------------------------------------------------------------
勝手に自己同一化しちゃいそうなおもしろさ、わたしこそが林真理子
--------------------------------------------------------------------------------
■エッセイスト林真理子、初体験
実は、このエッセイが林真理子初エッセイなのです──わたしにとって。
今まで読んだ林真理子作品というのもちょっと偏っていて『ミカドの淑女』だの『本を読む女』だの
ちょっと時代がかったまじめバージョン。
(『本を読む女』は切ないです。他力本願な本を読む女・・・あたしのことだ)
これが本領じゃないことは知っていながら
踏み込んだら帰ってこれないじゃないかという不安を呼ぶ刊行数。
そんなこんなで世間であれほど有名な作家でありながら、なかなか手が出なかったわけです。
今回はすみません、古本屋で手に入れました。
しばらく部屋のオブジェとなってから順番がめぐってきてさあ読書──
あ、という間でした。解説の通り。
■林真理子化現象
わたしはテレビをあまり見ない人だからなのか?
実は林真理子が色々騒がれているらしいことは知っていてもよくわかっていなかった。
なんでこの人が結婚するってだけでワイドショーなんだ?
と、実は思っていた。
なるほど。こーゆう理由があったのね。(何をいまさら・・・)
内容を読んでいても、このエッセイ、かなり古いことがわかる。
奥付見て・・・初版が昭和60年。
文庫になる前に単行本だったのだろうから、実際の刊行年代は少し前でしょう。
ということはわたしは**才・・・。
これ、そんな昔に「アリ」なんでしょうか、という本音本ですよね。
(本音かどうかはわからないですけど。
上手に手のひらで躍らさせられているのかも。そんな力でみなぎっている。
この場合の踊りは喜んで踊っちゃうけど。)
林真理子はこの中で自分のことを
「自分はナルシストだ」て言いきれる。
一番おもしろいのが『林真理子はなぜ林真理子か』ですよ。
言いきっちゃってでもわたし本当はかわいい女なのよーって必死で言ってみたり
でもどっかでするりとなんか「わかっちゃってたり」する。
えらいのは、というか頭いいのは、
あたしはこんなすごいのよっ、こんな女なのよって言いながら
自分の「世間一般の杓子定規からいけば変なところ、落ちこぼれなところ」ていうのを
ふんだんにスパイスきかせちゃうから、
読んでる側がついつい味方になってしまうところ。
すっかり、同化させていただきました。
わたしこそ、林真理子って。
ふつう、ある程度人っていうものは
「わたしは普通じゃない」
と思っているはず。
どこか特殊でどこか特別で──
そういった心をみごとにくすぐるわけです。
なんだ同じジャン──同じなわけないだろ、て林真理子は笑っていると思いますけど。
こーんな変だけどこーんなモテないけど(笑)でもあたしすごいのよ、って、そりゃすごい。
でもこれって多分コピーライター時代の作品なんだよね?
すでに小説の芽があるんですよね。
他の林小説、いってみようかなあ。
PR
作/長野まゆみ
画/鳩山郁子
出版社/作品社
ReviewWriteDate:2000/7/20
LastUpdate:2000/7/20
Notes:
天球儀文庫・アビと宵里のストーリー4編。
変わった小B6判ハードカバー。
この天球儀文庫はサイズも変わっている上に中の挿画も印象的。
必ず文中の語が英語やフランス語等で詩的にささやかれている。
つい日本語訳してしまう小市民なわたし──。
ヒトコトReview:
--------------------------------------------------------------------------------
アビと宵里、ふたりの一瞬の世界がせつない
--------------------------------------------------------------------------------
vol.1 月の輪船 A SICKLE BOAT
Story:
「この音が何に似ているのか、夏の間、ずっと考えていたんだ。ソォダ水はいつも飲んでいるのに、なんだか突然気にかかってサ。」──新学期、古代天球儀のある屋上で宵里がアビにこう云った。今夜は今年最後の野外映会。生徒たちのざわめきのなか、アビと宵里はソォダ水の記憶を確かめようと映写機のおいてある音楽室へと向かった──。
(口絵より)
■鳩のようにとべたなら
文中に出てくる「歌」です。
このシリーズはよく歌が出てきて詩で語るわけですが
この鳩のようにとべたならは逸品です。
なぜ──鳩なのだろう?
鳥は長野作品に多く出るモチーフのひとつです。
vol.2 夜のプロキシオン A PROCYON NIGHT
Story:
クリスマス休暇でにぎあう中央駅で、アビと宵里はとんでもないチビを拾ってしまった。チビにふりまわされる二人の上に、今年はじめての雪が舞い降りる……。
(口絵より)
■アビと宵里、日常。
クリスマスストーリーです。
アビが「ひっかけた」チビのせいで休暇先にいけなくなった二人、アビと宵里。
いつだって豪胆な少年にはなりきれないアビ。
ぐちぐち言いながらもやさしい宵里。
ふたりの関係がここちよい。
シリーズものとも知らず③銀星ロケットから読んでしまったわたしですが
銀星ロケットでもここちよい二人。
長野作品によくある
「ちょっと(表面的には)気の弱いでも芯のある少年」と
「一見豪胆で太陽の下で自分のためだけに生きているけれども、繊細な少年」
の組み合わせ。
実はわたしは全長野作品の中でこのアビと宵里ペアが一番好きです。
かれら二人の間には友愛以上の微妙な占有欲と
少年らしいほがらかさが同居していて
読者をどきりとさせるのです。
『新世界』なんかだとわかりやすすぎてつまらないんですね、わたしは。
■雪のピアノ
夜のプロキシオン、最大のオススメはやはり「チビ」天使のピアノ。
アビと宵里、そしてチビでのノエルの夜の時計塔でのシーン。
「ねえ、ピアノを弾いて、」から始まるシーン。
あああ、読んでよかった。でした、ほんとに。
よくあります、この1シーン、この1フレーズに出会えたからもうすべてOKになるような本。
もちろんこの夜のプロキシオンは「それだけじゃない」本ですが、何と言ってもこのシーンが一番でした。
見えない鍵盤、聞こえる音、でも聞こえない音。
ノエル。雪。ひく指はきっと冷たくなんかない──。
そして「チビ」が消え去ったあと、このピアノだけが残る。
その挿絵がなんとも言えない余韻を届けてくれます。
vol.3 銀星ロケット A LUNATIC ROCKET
Story:
街が花々で飾られ、楽しい計画がいっぱいのはずの復活祭。しかしそれは思わぬいざこざが起きかねない「気狂いじみた春」のおとずれでもあった……。
(口絵より)
■アビと宵里、相手と自分。
そんなわけで初めて読んだアビと宵里ストーリです。
実はシリーズのド真中から読み始めてしまったと知って得心してしまった
ふたりの関係でした。
いきなりこれじゃ、びっくりするわ。
このお話のメインはアビと宵里の喧嘩?(というか一方的にアビが宵里に対する占有欲に苦しむ)なのですが
それが復活祭、宵里の叔父、アビと宵里の兄たちを通じて語られて行くうちに
自分の中に有る同じような感情とはまってゆき、
すっかり世界にとりこまれてしまいました。
先の項にも書いたように、この二人、なんともいえずいい関係です。
アビは宵里が自分より宵里の叔父を優先させることで思い悩む。
宵里はそんなアビの気持ちを知っている。
だからこそ「どうしてそんなことを悩むんだよ」ぐらいの思いやりとも意地悪ともつかない態度をとる。
お互いにわかっていてでも微妙で。
喧嘩? ──喧嘩じゃないよね、これは。
お互いにちゃんと「知っている」のだから。
そういえば小学生の頃なんかは、友達が学校生活のすべてで喧嘩なんてしたら世界全滅状態だったなあ。
あの頃を思い出しました。
(今やそんなかわいい行動とりゃしない。世界から相手をぶったぎっちゃいますしねえ)
vol.4 ドロップ水塔 A BEACH TOWER WITH DROP
Story:
夏季休暇の一日目、あきらかに今日から天の色が違う。いつもと違う夏の終わりを予感しながら、二人はそれぞれの季節を歩きはじめた。──好評連作完結編。
(口絵より)
■アビと宵里、別れ。
わたしの大好きな、アビ&宵里がついにこのお話ではなればなれになります。
いつも通りの日々。空。空気。なのに変えてしまうのは不在の予感。
宵里自身がその実、恐れ不安にさいなまれている──そして、アビが力強い。
「まさか、ぼくが迷わないで決めたなんて思っていないだろう。」
アビは返事をしなかった。
(中略)
「……ほんとうは、さっきまで迷っていたんだ。アビに反対されたら、やめていたかもしれない。」
「……宵里は行くサ。ぼくが何と云っても。」
宵里はほんとうにアビが止めたら、一瞬は言葉につまってもそれを気づかせないぐらい自然に「それでもぼくは行くよ」と言っていたと思う。
アビが止めないからこそ出る、誘惑。
ここでひきとめたりしないアビが、素敵だ。
少女じゃない少年。だから長野世界だ。
アビと宵里はきっともう二度と逢わないんでしょう。
少なくとも今のまま、逢うことはない。
また他人から始めて、それでもお互いに「近づきたい」という感情がおこったならばそこで初めて出逢う。
そう、きっと物理的に再会したとしてもその時のそれぞれにとってお互いが必要じゃなければ、出逢いにはならない。どんなにかつて親しくても、その時の自分の生きかた、立場、想い、タイミングが合ってふたたび親しくなることなんてほんの奇跡。
でも、このふたりならそんな奇跡もみせてくれるはず──。
ぐじぐじ、読みてであるわたしのこころを痛ませる。
ぜひ、一読してほしいストーリーです。
画/鳩山郁子
出版社/作品社
ReviewWriteDate:2000/7/20
LastUpdate:2000/7/20
Notes:
天球儀文庫・アビと宵里のストーリー4編。
変わった小B6判ハードカバー。
この天球儀文庫はサイズも変わっている上に中の挿画も印象的。
必ず文中の語が英語やフランス語等で詩的にささやかれている。
つい日本語訳してしまう小市民なわたし──。
ヒトコトReview:
--------------------------------------------------------------------------------
アビと宵里、ふたりの一瞬の世界がせつない
--------------------------------------------------------------------------------
vol.1 月の輪船 A SICKLE BOAT
Story:
「この音が何に似ているのか、夏の間、ずっと考えていたんだ。ソォダ水はいつも飲んでいるのに、なんだか突然気にかかってサ。」──新学期、古代天球儀のある屋上で宵里がアビにこう云った。今夜は今年最後の野外映会。生徒たちのざわめきのなか、アビと宵里はソォダ水の記憶を確かめようと映写機のおいてある音楽室へと向かった──。
(口絵より)
■鳩のようにとべたなら
文中に出てくる「歌」です。
このシリーズはよく歌が出てきて詩で語るわけですが
この鳩のようにとべたならは逸品です。
なぜ──鳩なのだろう?
鳥は長野作品に多く出るモチーフのひとつです。
vol.2 夜のプロキシオン A PROCYON NIGHT
Story:
クリスマス休暇でにぎあう中央駅で、アビと宵里はとんでもないチビを拾ってしまった。チビにふりまわされる二人の上に、今年はじめての雪が舞い降りる……。
(口絵より)
■アビと宵里、日常。
クリスマスストーリーです。
アビが「ひっかけた」チビのせいで休暇先にいけなくなった二人、アビと宵里。
いつだって豪胆な少年にはなりきれないアビ。
ぐちぐち言いながらもやさしい宵里。
ふたりの関係がここちよい。
シリーズものとも知らず③銀星ロケットから読んでしまったわたしですが
銀星ロケットでもここちよい二人。
長野作品によくある
「ちょっと(表面的には)気の弱いでも芯のある少年」と
「一見豪胆で太陽の下で自分のためだけに生きているけれども、繊細な少年」
の組み合わせ。
実はわたしは全長野作品の中でこのアビと宵里ペアが一番好きです。
かれら二人の間には友愛以上の微妙な占有欲と
少年らしいほがらかさが同居していて
読者をどきりとさせるのです。
『新世界』なんかだとわかりやすすぎてつまらないんですね、わたしは。
■雪のピアノ
夜のプロキシオン、最大のオススメはやはり「チビ」天使のピアノ。
アビと宵里、そしてチビでのノエルの夜の時計塔でのシーン。
「ねえ、ピアノを弾いて、」から始まるシーン。
あああ、読んでよかった。でした、ほんとに。
よくあります、この1シーン、この1フレーズに出会えたからもうすべてOKになるような本。
もちろんこの夜のプロキシオンは「それだけじゃない」本ですが、何と言ってもこのシーンが一番でした。
見えない鍵盤、聞こえる音、でも聞こえない音。
ノエル。雪。ひく指はきっと冷たくなんかない──。
そして「チビ」が消え去ったあと、このピアノだけが残る。
その挿絵がなんとも言えない余韻を届けてくれます。
vol.3 銀星ロケット A LUNATIC ROCKET
Story:
街が花々で飾られ、楽しい計画がいっぱいのはずの復活祭。しかしそれは思わぬいざこざが起きかねない「気狂いじみた春」のおとずれでもあった……。
(口絵より)
■アビと宵里、相手と自分。
そんなわけで初めて読んだアビと宵里ストーリです。
実はシリーズのド真中から読み始めてしまったと知って得心してしまった
ふたりの関係でした。
いきなりこれじゃ、びっくりするわ。
このお話のメインはアビと宵里の喧嘩?(というか一方的にアビが宵里に対する占有欲に苦しむ)なのですが
それが復活祭、宵里の叔父、アビと宵里の兄たちを通じて語られて行くうちに
自分の中に有る同じような感情とはまってゆき、
すっかり世界にとりこまれてしまいました。
先の項にも書いたように、この二人、なんともいえずいい関係です。
アビは宵里が自分より宵里の叔父を優先させることで思い悩む。
宵里はそんなアビの気持ちを知っている。
だからこそ「どうしてそんなことを悩むんだよ」ぐらいの思いやりとも意地悪ともつかない態度をとる。
お互いにわかっていてでも微妙で。
喧嘩? ──喧嘩じゃないよね、これは。
お互いにちゃんと「知っている」のだから。
そういえば小学生の頃なんかは、友達が学校生活のすべてで喧嘩なんてしたら世界全滅状態だったなあ。
あの頃を思い出しました。
(今やそんなかわいい行動とりゃしない。世界から相手をぶったぎっちゃいますしねえ)
vol.4 ドロップ水塔 A BEACH TOWER WITH DROP
Story:
夏季休暇の一日目、あきらかに今日から天の色が違う。いつもと違う夏の終わりを予感しながら、二人はそれぞれの季節を歩きはじめた。──好評連作完結編。
(口絵より)
■アビと宵里、別れ。
わたしの大好きな、アビ&宵里がついにこのお話ではなればなれになります。
いつも通りの日々。空。空気。なのに変えてしまうのは不在の予感。
宵里自身がその実、恐れ不安にさいなまれている──そして、アビが力強い。
「まさか、ぼくが迷わないで決めたなんて思っていないだろう。」
アビは返事をしなかった。
(中略)
「……ほんとうは、さっきまで迷っていたんだ。アビに反対されたら、やめていたかもしれない。」
「……宵里は行くサ。ぼくが何と云っても。」
宵里はほんとうにアビが止めたら、一瞬は言葉につまってもそれを気づかせないぐらい自然に「それでもぼくは行くよ」と言っていたと思う。
アビが止めないからこそ出る、誘惑。
ここでひきとめたりしないアビが、素敵だ。
少女じゃない少年。だから長野世界だ。
アビと宵里はきっともう二度と逢わないんでしょう。
少なくとも今のまま、逢うことはない。
また他人から始めて、それでもお互いに「近づきたい」という感情がおこったならばそこで初めて出逢う。
そう、きっと物理的に再会したとしてもその時のそれぞれにとってお互いが必要じゃなければ、出逢いにはならない。どんなにかつて親しくても、その時の自分の生きかた、立場、想い、タイミングが合ってふたたび親しくなることなんてほんの奇跡。
でも、このふたりならそんな奇跡もみせてくれるはず──。
ぐじぐじ、読みてであるわたしのこころを痛ませる。
ぜひ、一読してほしいストーリーです。
作/長野まゆみ
出版社/河出書房新社
ReviewWriteDate:2000/7/20
LastUpdate:2000/7/20
Notes:
言わずと知れた長野まゆみデビュー作、『少年アリス』のおまけエピソード。
前半は長野まゆみ本人による『少年アリス』のイラストレーション。
後半が『三月うさぎのお茶会へ行く』。
Stoy:
あのL・キャロルの不思議の国でぼくらの少年アリスが大活躍…
三月うさぎのGreetingCollection
(帯より)
ヒトコトReview:
--------------------------------------------------------------------------------
おたのしみ本です、存分に楽しみましょう
--------------------------------------------------------------------------------
■少年アリス、イラストにて登場
長野まゆみは一時マンガ家をめざしていた人です。
そんなわけで最近は多くの単行本を自分の挿画で出版しているのですが
初期は別の作家や装丁屋さんに任せています。
デビュー作である『少年アリス』もそういったわけで実際には1枚の挿画もない
シンプルな世界となっているわけです。
このおたのしみ本ではそんな『少年アリス』のストーリーが
まるごと著者本人によるイラストでかざられている、という珍しいもの。
挿画というのは読むときのイメージをふくらませる一方、
しっかりと形作ってしまうという面もあります。
長野まゆみ自身、はじめは自分で挿画を入れることにためらいがあったようですが、
彼女に関する限り世界観とまったく違っているわけではないので
抵抗感なく読み進めることができます。
それにしてもこの本、単なる挿絵じゃなくって、
本当に『少年アリス』の筋を追ってイラストのみで前半が進んで行くわけで、
ファンサービスといいますか
ファン以外じゃ何だかさっぱりわからなくても平然としてしまうような
一種の世界観といのがあって、面白い。
わたしはすでに『少年アリス』も読んでいるしとても好きな作品でもあるし、ファンです。
でもファンでなくても手に取りそうな装丁のくせに
それ以外は知らん振りで、
こりゃ、『少年アリス』読まなきゃいかんでしょう、という感じですから。
■お茶会を読んだらあとは本編へ
そして後半のショートストーリーですが
個人的にはもっと蜜蜂に出て欲しかった!
ですがファン以外でも楽しめる小作。
久々に『少年アリス』本編を読みたくなりました。
(そのうち過去の読書レビューもしたいものですがはたして過去まで戻れるのでしょうか??)
今回の気になるフレーズは…
アリスはまっすぐに進む道を選んだ。
この場に蜜蜂がいたらい、おそらくその道を進むのではないかと考えたからだ。
アリスと蜜蜂、そして蜜蜂の兄。
成長した彼らに会いたいという想いと、決して移ろわない過去の景色だからこその長野作品。
わたしの野望はかなえられないでしょう。
出版社/河出書房新社
ReviewWriteDate:2000/7/20
LastUpdate:2000/7/20
Notes:
言わずと知れた長野まゆみデビュー作、『少年アリス』のおまけエピソード。
前半は長野まゆみ本人による『少年アリス』のイラストレーション。
後半が『三月うさぎのお茶会へ行く』。
Stoy:
あのL・キャロルの不思議の国でぼくらの少年アリスが大活躍…
三月うさぎのGreetingCollection
(帯より)
ヒトコトReview:
--------------------------------------------------------------------------------
おたのしみ本です、存分に楽しみましょう
--------------------------------------------------------------------------------
■少年アリス、イラストにて登場
長野まゆみは一時マンガ家をめざしていた人です。
そんなわけで最近は多くの単行本を自分の挿画で出版しているのですが
初期は別の作家や装丁屋さんに任せています。
デビュー作である『少年アリス』もそういったわけで実際には1枚の挿画もない
シンプルな世界となっているわけです。
このおたのしみ本ではそんな『少年アリス』のストーリーが
まるごと著者本人によるイラストでかざられている、という珍しいもの。
挿画というのは読むときのイメージをふくらませる一方、
しっかりと形作ってしまうという面もあります。
長野まゆみ自身、はじめは自分で挿画を入れることにためらいがあったようですが、
彼女に関する限り世界観とまったく違っているわけではないので
抵抗感なく読み進めることができます。
それにしてもこの本、単なる挿絵じゃなくって、
本当に『少年アリス』の筋を追ってイラストのみで前半が進んで行くわけで、
ファンサービスといいますか
ファン以外じゃ何だかさっぱりわからなくても平然としてしまうような
一種の世界観といのがあって、面白い。
わたしはすでに『少年アリス』も読んでいるしとても好きな作品でもあるし、ファンです。
でもファンでなくても手に取りそうな装丁のくせに
それ以外は知らん振りで、
こりゃ、『少年アリス』読まなきゃいかんでしょう、という感じですから。
■お茶会を読んだらあとは本編へ
そして後半のショートストーリーですが
個人的にはもっと蜜蜂に出て欲しかった!
ですがファン以外でも楽しめる小作。
久々に『少年アリス』本編を読みたくなりました。
(そのうち過去の読書レビューもしたいものですがはたして過去まで戻れるのでしょうか??)
今回の気になるフレーズは…
アリスはまっすぐに進む道を選んだ。
この場に蜜蜂がいたらい、おそらくその道を進むのではないかと考えたからだ。
アリスと蜜蜂、そして蜜蜂の兄。
成長した彼らに会いたいという想いと、決して移ろわない過去の景色だからこその長野作品。
わたしの野望はかなえられないでしょう。
作/パウロ・コエーリョ
訳/山川紘矢+山川亜希子
出版社/角川文庫
ReviewWriteDate:2000/7/17
LastUpdate:2000/7/17
Notes:
作者、パウロ・コエーリョはブラジル人。作品はスペイン語で書かれている。
『星の巡礼』(角川文庫)で有名。だそうです。
Stoy:
スペインの小さな田舎街で教鞭を執る29歳のピラールは、12年ぶりに再会した幼なじみの男性から愛を告白される。病を治す力をもつ修道士の彼は、彼女に自分と一緒に来てほしいという。今の暮らしを捨てる決心がつかずに悩むピラールだったが、彼との旅を通して真実の愛と神の力を再発見してゆく……。
(帯より)
ヒトコトReview:
--------------------------------------------------------------------------------
キリスト教的背景と普遍的な想いとの交差。バランスは難しい……
--------------------------------------------------------------------------------
■圧倒的な冒頭、これだけで実は満足です
小説の冒頭(はしがき除く)、すばらしい文章です。
実はタイトル買いしてしまったこの本ですが、この文章が読めただけでとりあえず満足。
少し長いですが引用・・・
訳者さま、ありがとう。
こんなにきれいに訳していただいて。これがなかったらこの本はずっと難解になっていたと思う。
冒頭でぐいとこの「想い」を脳裏に焼き付けてくれたからこそ
その後の謎な思いにも耐えられたといいますか──。
■キリスト教(宗教)と小説
これは修道士の「彼」と主人公ピラールのお話。
この本はどうしてもこの宗教観から逃げることは出来ません。
はしがきで著者が
「神は形式のもとにいるのではなく、祈るもの次第でどこにでもいる。宗教は形ではない」
といった意のことを言っているのですが
まさしくそれはその通りだと共感することができるのですが
やはり全体を通して宗教を背負っていないわたし(というか多くの日本人)には
どうにもなじめない話題では在りました。
言いたい意味、思いは言葉として伝わるのに、リアリティと実感がともなわないのは
バックボーンの問題なのでしょう。
神=男性ではなく神=女性・母性・マリアという転換は
背景に信仰もしくは信仰を持っていた過去があればもっとぐっと内面をえぐるもののはずなのに
どうにもさらっと読んでしまいました。
だからピラールの中で信仰が戻って来ると言われてもピンと来ない。
恐らくストーリーを推し進めるキーであるはずなのに。
こう考えると小説だとか映画だとかそういった創作物というのは
否応無しにそのバックボーンを背負って、必ず縛りを持って、対象としたある一定の人間により訴えるものでしかないのですね。
より普遍的な話題になれば別なんでしょうし、もっとすごい才能からすれば打ち破るのは可能なのかもしれない。
ただ、やはりそれには限界があって、どっかで「誰々向け」「何々向け」担ってしまうんじゃないでしょうか。
そういったジャンル分け嫌いなんですが、それも有りなのかな、としみじみ思いました。
特に一般的な日本人にとっての、神様っていうのは信仰しつづけるもの、というよりは
つねにそこに「いて」たまに悪戯さえしかけてくる八百万の神みたいなベースがあるように思います。
だからキリスト教的な信仰からは自然遠くなってしまうんでしょうね。
(あくまで私の主観です)
あと「愛」という言葉の捕らえ方も、もしかしたら微妙なのかも、と思いました。
■『他者』と自分の境界線
話の骨子はこの
「宗教・祈りは形式ではない=修道院にいることでも戒律をまもることでもない」
というのと
「危険を冒すことを恐れては人生は変わらない。自分を抑制している『他者』を自分から追い出して、『魔法の瞬間』を見逃さないよう正しく生きて行く」
ということなのですが
後者に関しては身につまされました。
自分がこの『他者』の存在を知っているから。
途中ピラールが「どうしてわたしはこんなに頑張って自分がなりたくないものになろうと努力してきたのだろう」と思うくだりがあるのですが、わたしも振り返ればそんな日々です。
日本語としてあまりすんなりと意識に入ってきにくい『他者』ですが──はて原文ではこの『他者』というのはどういう単語で表現されているのでしょう? ──意味、意義、思いは伝わってきました。
明日から自分が変わることはないですが。
というか、もちろんそんなこと大昔から自覚済ですので…とするとわたしは大変ずるいんでしょうねえ。(笑)
■ネタばれですが──「彼」とピラールの想い
ちょっと驚いたのは、ネタ。
マリアの声を聞き奇跡を起こせる修道士の「彼」は
「愛する幼馴染とのひとりの人間としての生活」と「伝統的宗教生活」との間で迷い、
決断をするためにピラールと再会していたのでした。
おいおい、そりゃないだろー、とピラール弁護のわたし。
でも、人なら「もしかしたらそうなったかもしれない自分」に賭けてみたくなるのかも知れません。
結果、伝統的宗教生活にとらわれるよりピラールへの愛を優先させた「彼」は
奇跡もマリアの声も手放してピラールの元に戻っているわけです──。
いや、上のネタには正直フイをつかれました。
迷いながら、だからこそ自分試すために女に会いに来るとは──と。
ピラールがマジで「彼」に惚れても自分にとっては宗教生活が大切だったら
嵐だけまきおこしてとっとと修道院に戻るつもりだったのね、あんた!
さすが男性作者、女のわたしじゃ思いもつきませんでした。
女の読者なんてものは自分がこうされたいという理想像を求めて読んでいるので
「女」がそんな踏絵にされるなんて思わずに読んでいるわけですから。
女性が自分を試すために男性に会いに行くなら平然と読んでたと思います。
ああ感動──なはずなんですが。
実はわたし、本を半分ほど読むまで気づきませでした。
「彼」は「彼」でしかなくて、名前、ないんですね──。
というかこの小説では名前が出てこない。
のっぺらぼうの、「彼」。
さてこれはお話の問題なのでしょうか?
それとも訳文の問題?
正直、この「彼」がピラールを愛しているっていうのは本当に文字通りだけで
想いがともなっていない小説上の設定っていう気がする。
「彼」には個性もなんも、感じられないのです。
だからそんな「彼」を愛するようになるピラールの想いも説得力がない。
いったい魅力は何なんだね?
それは主に宗教的瞬間を分かち合うことで進んでいるように見えるので
やはり宗教観の乏しいわたしには理解できないのか?
ただ、どうも小説としてきっちりと描くべき「人」がないままに話が進んで行くので
結局よくわかならい──という結果になっているような気がします。
先に「他者に関する記述が思い当たった」と書きましたが
文章を読んで文章から自分はそう読み取ることで思い当たりましたが、
「おうおう、そうなんだよー」という感情論で言うならば、小説になっていない気がします、他者の逸話。
これは宗教観をともなったヒーリング本なんだって言いきってしまえばこれでもいいんでしょうが
小説にはなりえてないな、というのが実感です。
話し言葉もモンキリだから、誰がしゃべってんだかさっぱりわからないし。
それにしてもこういう外国文学の主人公の女性って
どうしていつも同じなのかなー?
多分、間違いなく訳文なんだろうな──なんて、思いました。
ただまあ、あとで読み返すと「変わる」かもしれないお話では有ります。
その人のその時のコンディションによって、想いが変わるような、そういった奥深さは感じました。
しばらくしたらまた読んでみよっと。
訳/山川紘矢+山川亜希子
出版社/角川文庫
ReviewWriteDate:2000/7/17
LastUpdate:2000/7/17
Notes:
作者、パウロ・コエーリョはブラジル人。作品はスペイン語で書かれている。
『星の巡礼』(角川文庫)で有名。だそうです。
Stoy:
スペインの小さな田舎街で教鞭を執る29歳のピラールは、12年ぶりに再会した幼なじみの男性から愛を告白される。病を治す力をもつ修道士の彼は、彼女に自分と一緒に来てほしいという。今の暮らしを捨てる決心がつかずに悩むピラールだったが、彼との旅を通して真実の愛と神の力を再発見してゆく……。
(帯より)
ヒトコトReview:
--------------------------------------------------------------------------------
キリスト教的背景と普遍的な想いとの交差。バランスは難しい……
--------------------------------------------------------------------------------
■圧倒的な冒頭、これだけで実は満足です
小説の冒頭(はしがき除く)、すばらしい文章です。
実はタイトル買いしてしまったこの本ですが、この文章が読めただけでとりあえず満足。
少し長いですが引用・・・
ピエドラ川のほとりで私は泣いた。この川の水の中に落ちたのもは、木の葉も虫も、鳥の羽さえも、岩に姿を変えて、川底に沈むと言い伝えられている。心を胸の中から取り出して、流れの中に投げ込めるものならば、恋もこの苦しみも終わって、私はすべてを忘れることができるだろうに。
ピエドラ川のほとりにすわって、私は泣いた。冬の空気がわたしのほおの涙を冷し、その冷たい涙は、目の前の流れの中へはらはらと落ちて行った。この川はどこかでもう一つの川と合流し、さらにまた、別の川と合流して、私の心からも視野からもずっと離れたところで、海と一つになるのだ。
私の涙もまた、ずっと遠くまで流れてゆきますように。そして私が、かつて彼を思って泣いたことを、私の愛が思い出しませんように。
訳者さま、ありがとう。
こんなにきれいに訳していただいて。これがなかったらこの本はずっと難解になっていたと思う。
冒頭でぐいとこの「想い」を脳裏に焼き付けてくれたからこそ
その後の謎な思いにも耐えられたといいますか──。
■キリスト教(宗教)と小説
これは修道士の「彼」と主人公ピラールのお話。
この本はどうしてもこの宗教観から逃げることは出来ません。
はしがきで著者が
「神は形式のもとにいるのではなく、祈るもの次第でどこにでもいる。宗教は形ではない」
といった意のことを言っているのですが
まさしくそれはその通りだと共感することができるのですが
やはり全体を通して宗教を背負っていないわたし(というか多くの日本人)には
どうにもなじめない話題では在りました。
言いたい意味、思いは言葉として伝わるのに、リアリティと実感がともなわないのは
バックボーンの問題なのでしょう。
神=男性ではなく神=女性・母性・マリアという転換は
背景に信仰もしくは信仰を持っていた過去があればもっとぐっと内面をえぐるもののはずなのに
どうにもさらっと読んでしまいました。
だからピラールの中で信仰が戻って来ると言われてもピンと来ない。
恐らくストーリーを推し進めるキーであるはずなのに。
こう考えると小説だとか映画だとかそういった創作物というのは
否応無しにそのバックボーンを背負って、必ず縛りを持って、対象としたある一定の人間により訴えるものでしかないのですね。
より普遍的な話題になれば別なんでしょうし、もっとすごい才能からすれば打ち破るのは可能なのかもしれない。
ただ、やはりそれには限界があって、どっかで「誰々向け」「何々向け」担ってしまうんじゃないでしょうか。
そういったジャンル分け嫌いなんですが、それも有りなのかな、としみじみ思いました。
特に一般的な日本人にとっての、神様っていうのは信仰しつづけるもの、というよりは
つねにそこに「いて」たまに悪戯さえしかけてくる八百万の神みたいなベースがあるように思います。
だからキリスト教的な信仰からは自然遠くなってしまうんでしょうね。
(あくまで私の主観です)
あと「愛」という言葉の捕らえ方も、もしかしたら微妙なのかも、と思いました。
■『他者』と自分の境界線
話の骨子はこの
「宗教・祈りは形式ではない=修道院にいることでも戒律をまもることでもない」
というのと
「危険を冒すことを恐れては人生は変わらない。自分を抑制している『他者』を自分から追い出して、『魔法の瞬間』を見逃さないよう正しく生きて行く」
ということなのですが
後者に関しては身につまされました。
自分がこの『他者』の存在を知っているから。
途中ピラールが「どうしてわたしはこんなに頑張って自分がなりたくないものになろうと努力してきたのだろう」と思うくだりがあるのですが、わたしも振り返ればそんな日々です。
日本語としてあまりすんなりと意識に入ってきにくい『他者』ですが──はて原文ではこの『他者』というのはどういう単語で表現されているのでしょう? ──意味、意義、思いは伝わってきました。
明日から自分が変わることはないですが。
というか、もちろんそんなこと大昔から自覚済ですので…とするとわたしは大変ずるいんでしょうねえ。(笑)
■ネタばれですが──「彼」とピラールの想い
ちょっと驚いたのは、ネタ。
マリアの声を聞き奇跡を起こせる修道士の「彼」は
「愛する幼馴染とのひとりの人間としての生活」と「伝統的宗教生活」との間で迷い、
決断をするためにピラールと再会していたのでした。
おいおい、そりゃないだろー、とピラール弁護のわたし。
でも、人なら「もしかしたらそうなったかもしれない自分」に賭けてみたくなるのかも知れません。
結果、伝統的宗教生活にとらわれるよりピラールへの愛を優先させた「彼」は
奇跡もマリアの声も手放してピラールの元に戻っているわけです──。
いや、上のネタには正直フイをつかれました。
迷いながら、だからこそ自分試すために女に会いに来るとは──と。
ピラールがマジで「彼」に惚れても自分にとっては宗教生活が大切だったら
嵐だけまきおこしてとっとと修道院に戻るつもりだったのね、あんた!
さすが男性作者、女のわたしじゃ思いもつきませんでした。
女の読者なんてものは自分がこうされたいという理想像を求めて読んでいるので
「女」がそんな踏絵にされるなんて思わずに読んでいるわけですから。
女性が自分を試すために男性に会いに行くなら平然と読んでたと思います。
ああ感動──なはずなんですが。
実はわたし、本を半分ほど読むまで気づきませでした。
「彼」は「彼」でしかなくて、名前、ないんですね──。
というかこの小説では名前が出てこない。
のっぺらぼうの、「彼」。
さてこれはお話の問題なのでしょうか?
それとも訳文の問題?
正直、この「彼」がピラールを愛しているっていうのは本当に文字通りだけで
想いがともなっていない小説上の設定っていう気がする。
「彼」には個性もなんも、感じられないのです。
だからそんな「彼」を愛するようになるピラールの想いも説得力がない。
いったい魅力は何なんだね?
それは主に宗教的瞬間を分かち合うことで進んでいるように見えるので
やはり宗教観の乏しいわたしには理解できないのか?
ただ、どうも小説としてきっちりと描くべき「人」がないままに話が進んで行くので
結局よくわかならい──という結果になっているような気がします。
先に「他者に関する記述が思い当たった」と書きましたが
文章を読んで文章から自分はそう読み取ることで思い当たりましたが、
「おうおう、そうなんだよー」という感情論で言うならば、小説になっていない気がします、他者の逸話。
これは宗教観をともなったヒーリング本なんだって言いきってしまえばこれでもいいんでしょうが
小説にはなりえてないな、というのが実感です。
話し言葉もモンキリだから、誰がしゃべってんだかさっぱりわからないし。
それにしてもこういう外国文学の主人公の女性って
どうしていつも同じなのかなー?
多分、間違いなく訳文なんだろうな──なんて、思いました。
ただまあ、あとで読み返すと「変わる」かもしれないお話では有ります。
その人のその時のコンディションによって、想いが変わるような、そういった奥深さは感じました。
しばらくしたらまた読んでみよっと。
作/夢枕獏
出版社/文芸春秋
ReviewWriteDate:2000/7/17
LastUpdate:2000/7/17
Notes:
おなじみ、夢枕獏氏の『陰陽師』です。ちなみに最新刊ではない…
Story:
悪魔 妖魔 何するものぞ! 都の闇に巣食う魑魅魍魎に挑む若き陰陽博士・安倍晴明と貴公子・源博雅。胸のすく冒険譚!
(帯より)
ヒトコトReview:
--------------------------------------------------------------------------------
ここちよい予定調和に酔う
--------------------------------------------------------------------------------
文庫になっている陰陽師はすでに読んでいるものの
単行本には初挑戦です。いや、内容が違うわけではないのですが財布には痛いです。(涙)
でも相変わらず面白かったです。
というか陰陽夜話(第三夜・第四夜)に行った後だからでしょうか、
以前文庫を読んだときよりすんなり世界に入ることが出来ました。
これまた大好きな役者さまのお芝居で上演される演目がこの巻に入っていたから・・・
という不埒な理由の読書でありました。。。
■パターンと描写・心地よい予定調和
夢枕獏・岡野玲子対談で夢枕氏が
「つかず離れず、いつ読んでも大体同じレベルの博雅と清明がいるようにしているんです」(『KAWADE夢ムック 安倍晴明』)
と言っているように、
どこをきっても同じ二人、これが水戸公門ばりの予定調和で心地よい。
晴明の屋敷の庭の描写・博雅の訪問・酒の描写・呪の話
例の「ゆこう」「ゆこう」「そういうことになった」のくだり。
晴明と博雅の会話。
確信犯でこれ書いてるんだから、相当楽しかろう──とうらやましい。
わたしはお話の頭のこの予定調和だけでほくそ笑んでしまう。
■短編の極意(笑)
そしてまたわたしが好きなのが短編ならではのヤマの張り。
どれを読んでも必ずちゃんと「残せる」のがすごい。
毎回やられた、と思うわけです。
今回は個人的に『ものや思ふと……』にやられてしまった。
丁度岡野版陰陽師で同じ歌合せの話を時間差で読んでいて、
色々と思うところ在り。お話というのは無限ですね……
■陰陽師はやりについて
今や本屋に行けば陰陽師・安倍晴明で溢れています。
ちょっと前だと考えられなったこと。
いかんせん、わたしの中の晴明は夢枕氏の晴明以前にヒゲのオジさんがいたりするので、
リハビリが大変です。涙。
世紀末と末法思想がまぜこぜになって吹いているのは
間違いじゃないんでしょうね。
ただ、京都の晴明神社に行って思ったのが、
「想い」より先行してしまった「流れ」といいますか「思いこみ」のようなもの。
難しいですねえ、歴史上の人物が人気者?になるというのは。
例えば新撰組であったり源義経だったりすると思いますが、
歴史上の人物っていうのは限りなく架空の人物たり得てしまうわけです。
まあ著作権?もへったくれもないんだからいいんでしょうが、
どうにも不思議な感じです。
かくゆうわたしも同類なのですが──(笑)。
ちなみに義経は『義経記』のノリが面白いです。
静御前一筋なんて大嘘でぞろぞろ女人つれて逃亡する辺り、まさかテレビじゃやれないでしょうが。
■陰陽夜話
ちなみに陰陽夜話の感想、というかヒトコト。
夢枕獏氏は今までのイメージとは違いニコニコいいオジさんでした。
きっとモノ書くときはがらりと別人格でしょう。
岡野玲子さんは作品どおり才気溢れる才媛といった感じで直衣(狩衣だったかな、記憶が遠い)に烏帽子姿で和琴を弾いていました。
正直和琴の腕前っていうのは聞いていてもさっぱりわからないのですが(筝とは別物ですね、琴とは言っても──と、わたしは筝の人)弦少ないんですねえ。おきれいな方でした。
ちなみに『8』(キャサリン・ネヴィル)を読むとピタゴラスの音階とか出てきて面白いかと思います。
夜話でちょっと話が出ていましたが。
出版社/文芸春秋
ReviewWriteDate:2000/7/17
LastUpdate:2000/7/17
Notes:
おなじみ、夢枕獏氏の『陰陽師』です。ちなみに最新刊ではない…
Story:
悪魔 妖魔 何するものぞ! 都の闇に巣食う魑魅魍魎に挑む若き陰陽博士・安倍晴明と貴公子・源博雅。胸のすく冒険譚!
(帯より)
ヒトコトReview:
--------------------------------------------------------------------------------
ここちよい予定調和に酔う
--------------------------------------------------------------------------------
文庫になっている陰陽師はすでに読んでいるものの
単行本には初挑戦です。いや、内容が違うわけではないのですが財布には痛いです。(涙)
でも相変わらず面白かったです。
というか陰陽夜話(第三夜・第四夜)に行った後だからでしょうか、
以前文庫を読んだときよりすんなり世界に入ることが出来ました。
これまた大好きな役者さまのお芝居で上演される演目がこの巻に入っていたから・・・
という不埒な理由の読書でありました。。。
■パターンと描写・心地よい予定調和
夢枕獏・岡野玲子対談で夢枕氏が
「つかず離れず、いつ読んでも大体同じレベルの博雅と清明がいるようにしているんです」(『KAWADE夢ムック 安倍晴明』)
と言っているように、
どこをきっても同じ二人、これが水戸公門ばりの予定調和で心地よい。
晴明の屋敷の庭の描写・博雅の訪問・酒の描写・呪の話
例の「ゆこう」「ゆこう」「そういうことになった」のくだり。
晴明と博雅の会話。
確信犯でこれ書いてるんだから、相当楽しかろう──とうらやましい。
わたしはお話の頭のこの予定調和だけでほくそ笑んでしまう。
■短編の極意(笑)
そしてまたわたしが好きなのが短編ならではのヤマの張り。
どれを読んでも必ずちゃんと「残せる」のがすごい。
毎回やられた、と思うわけです。
今回は個人的に『ものや思ふと……』にやられてしまった。
丁度岡野版陰陽師で同じ歌合せの話を時間差で読んでいて、
色々と思うところ在り。お話というのは無限ですね……
■陰陽師はやりについて
今や本屋に行けば陰陽師・安倍晴明で溢れています。
ちょっと前だと考えられなったこと。
いかんせん、わたしの中の晴明は夢枕氏の晴明以前にヒゲのオジさんがいたりするので、
リハビリが大変です。涙。
世紀末と末法思想がまぜこぜになって吹いているのは
間違いじゃないんでしょうね。
ただ、京都の晴明神社に行って思ったのが、
「想い」より先行してしまった「流れ」といいますか「思いこみ」のようなもの。
難しいですねえ、歴史上の人物が人気者?になるというのは。
例えば新撰組であったり源義経だったりすると思いますが、
歴史上の人物っていうのは限りなく架空の人物たり得てしまうわけです。
まあ著作権?もへったくれもないんだからいいんでしょうが、
どうにも不思議な感じです。
かくゆうわたしも同類なのですが──(笑)。
ちなみに義経は『義経記』のノリが面白いです。
静御前一筋なんて大嘘でぞろぞろ女人つれて逃亡する辺り、まさかテレビじゃやれないでしょうが。
■陰陽夜話
ちなみに陰陽夜話の感想、というかヒトコト。
夢枕獏氏は今までのイメージとは違いニコニコいいオジさんでした。
きっとモノ書くときはがらりと別人格でしょう。
岡野玲子さんは作品どおり才気溢れる才媛といった感じで直衣(狩衣だったかな、記憶が遠い)に烏帽子姿で和琴を弾いていました。
正直和琴の腕前っていうのは聞いていてもさっぱりわからないのですが(筝とは別物ですね、琴とは言っても──と、わたしは筝の人)弦少ないんですねえ。おきれいな方でした。
ちなみに『8』(キャサリン・ネヴィル)を読むとピタゴラスの音階とか出てきて面白いかと思います。
夜話でちょっと話が出ていましたが。
作/ブラッド・フレイザー
演出/宮本亜門
ReviewWriteDate:2000/7/11
LastUpdate:2000/7/11
Cast:木村佳乃(キャンディ)/増沢望(デヴィッド)/橋本さとし(バーニー)/笠原浩夫(ロバート)/明星真由美(ジェリィ)/平宮博重(ケイン)/天野小夜子(ベニータ)
Tokyo 2000.7.1~16 @パルコ劇場
Osaka 2000.7.19~23 @シアター・ドラマシティ
Date:2000/7/9 13:00 Y13
Note:
93年に宮本亜門の演出で上演され、内容の過激さでセンセーショナルな話題を呼んだ作品を、新キャストで再演する。(シアターガイドより)
ただし96年に脚本が改訂になっている為今回の公演は改訂版の上演となる。
※ベニータ役の天野小夜子のみ初演と同じ。
Story
新刊本の書評を書く仕事をしているキャンディは、ウェイターの元恋人のデヴィッドと同居中。ゲイであることを告白した彼と親友として同居しているのだ。そんなデヴィッドは友人で妻帯者のバーニーへ想いを寄せているが、バーニーはゲイではない。キャンディは拒食症に悩みつつも、バーテンのロバート、同じジムに通うレズビアン・ジェリィに言い寄られ、つきあい出す。そんな中、エドモントンの街に連続婦女暴行事件が発生する──
ヒトコトReview:
--------------------------------------------------------------------------------
主役は木村キャンディじゃない!! 増沢デヴィッド&橋本バーニーこそが主役也!
--------------------------------------------------------------------------------
えんぺで酷評されていたので多少構えて観劇してしまいました。
感想としてはすんなりと「あれ、おもしろいじゃん」です。
ただよくよくその「おもしろい」を掘り下げて見ると確かにおかしいのかもしれません。
わたしがおもしろいと感じたポイントをかいつまんで言うと
・なんといっても増沢デヴィッド&橋本バーニー!!
・なんとなく感じさせられるどうしようもない閉塞感
てことなんです。
上記ヒット項目の解説はあとにまわすとして、先に?の部分から。
■悲しいかな、主人公キャンディに共感できない
どうしようもない女のイヤな部分を描いているわけだから、
同性であるわたしは自分を見ているようでもちろんイヤになるのは当たり前なのですが、
「ああわたしもこんなヤナ奴だよ。だからキャンディがそうしちゃうのわかるよ」
ていう思いは湧き起こりませんでした。(これを共感と呼ぶと思う)
「この子は理解できん。この子はおかしい!」
て思ってしまいました。
それが脚本と演出の狙いだったなら、ずばり引っかかっています。
でも多分、それは狙いじゃないですよね?
わたしの狭量な発想かもしれないけれど
「キャンディはこんなにデヴィッドが好きなのに報われない
(とパンフにあるからそうなんだろう。ちっともそんな感じはしなかったけど。甘い伏線はあるけどさ)。
だから拒食症にもなるし(これも頭の伏線のみだから忘れそう。ピザ食ってるぞ! て思いませんでした? まあパンフには拒食症が肩書なんでそうなんでしょう)
そんなに好きじゃない人とでも関係を持ちたいんだ。わかるよ、わかる!」
て共感させないといけないんだと思うのです、とりあえず女性の観客は。
もしかしたらわたしが模範的女性観客じゃないのでしょうか?
ただ、キャンディの描き方がちょっと全編通して甘かったような。
デヴィッド&バーニー(異端・異常)に対するキャンディ(普通)なのはわかるのですがなんとも中途ハンパに存在してしまっていました。
そもそも3人がキーの物語なのに、宣伝が木村佳乃中心だからダントツの主人公だと思って見に行くわけじゃないですか。
で、結局主人公にはなりえてなかったと思うので。
途中からうまく舞台がノって来たのでキャンディが生きてはきましたが
まあ元気なねーちゃんという意味でしかなかった。
木村嬢の演技は悪くはなかったです。
ただガツンと来るこないが役柄の問題なのか演技の問題なのかは
見当がつきませんので言及は避けます。
もし「ただただ普通のイヤなところをもった女の子」
という役を描きたかったのなら正解なのだと思います。伝わりにくいですが。
キャンディが伝わらないので
キャンディを介して伝わるべくデヴィッド&バーニーが突出してしまい
わたしの目はもうその2人だけにくぎ付けでした。
あと、バーニーの奇怪な行動の意味理由っていうのが
わかるようでわからない。
わかると感じる部分は橋本バーニーの力であって、
脚本を読んだだけだと首をひねっていたかもしれないです。
ただまあ、役者が存在してはじめて演劇だと思うのでそれでよいのかもしれませんが。
ところでキャンディの友達で自殺をしてしまった子って
キャンディにとって何だったんでしょうね?(まあ友達なのはわかりますが)
彼女の死にあれだけ反応を示しながら
その死によっては何の影響も受けていないようなキャンディ。
(叫ぶ・独白の部分はあからさまにわかりますが)
やっぱり曖昧模糊としたままです・・・
■休憩時間の入り方が切ない・・・
どうしても気になったこと。
おそらく会場の全員が思ったと思うのですが、休憩時間。
たしかに長いお芝居ではありましたが「どうしてここで!?」というシーンでした。
盛り上がりがそこで分断されてしまうのです。
で、盛り上がって叫んでいたキャストが
ちょっとは暗いが肉眼でばっちり見える舞台上を
てくてく消えてゆくのです。
あああああ、なんてことでしょう。
せめて完全な暗転にしてキャスト去らせてから休憩にしてほしかったです。
■増沢デヴィッド&橋本バーニー、素敵!!!
というか、わたし個人はもう橋本バーニーしか見ていなかった。
とにかく目を惹く圧倒的な存在感。
パルコ劇場って決して小さな箱ではないと思うのですが
めらめら気を感じました。
まあ席が近いからかもしれませんが。
ちょっとした所作等、目をひきます。
そのバーニーの相手役である増沢デヴィッドは
「滅茶苦茶やっててイヤなヤツ」をうまいこと伝えた上で
「でもとてもナイーヴ」と攻めてくるので、勝てっこありません。
ふたりが建物の上の方で語り合うシーン、絶妙です。
デヴィッドのバーニーへの思いは愛というか恋なんだけれども
バーニーのそれがはっきりわからないまでも
デヴィッドの存在が簡単なものでないことは痛いほど伝わります。
■どこまでも続く閉塞感
パンフにもあったのですが、初演の1993年より今の時代の方が閉塞感に満ちていると思います。
だからでしょうか? この
「どこにも出ていけない、どこにも出ていかない」
澱んだ空気が、否定するより先に根っこにひっかかって納得させられてしまう。
凶悪事件だったりセクシャリティの問題だったり色々とあるとは思いますが
それ以上にどうにかしたいという思いがあっても
その思いがパワーには結びつかなくてただ「そこにいる」ていう感じが
「今のわたし」には心地よかったです。
■各キャストへの感想
木村佳乃(キャンディ)
上記の通りです。でも身体ほそいね、きれいだねー。
わりに顔がおおきくて驚きました。
増沢望(デヴィッド)
わがままで切なくてナイーヴで放っておけない彼。
観客であるわたしもすっかり彼に翻弄されてしまいました。
ふーん、俳優座なんだ。
橋本さとし(バーニー)
元・新感線、だそうです。
今まで彼のことを知らなかったのが恥ずかしい。テレビも見ないしなあ。
わたしにとってのこの公演はイコール橋本さとしLOVE!です。
わきに立っているだけでも目をそらせませんでした。
笠原浩夫(ロバート)
スタジオライフ所属の花形。
今回はスタジオライフの笠原さん分優先予約でチケットを取りました。
女性とからんでいる笠原さん、はじめてみました。
やっぱり長身だと得ですね、舞台映えします。
初の外部出演でしたが、まあいつも通りナイーヴな彼でした。
明星真由美(ジェリィ)
NODAMAP農業少女出るんですね。
すっかりキャンディが食われていましたが、まあそういう役なのかもしれません。
平宮博重(ケイン) →のちの成宮寛貴である(笑)
この公演の為のオーディションで選ばれた彼。
いきなり変なことまでさせられてちょっと可哀想。役者って大変だね(笑)。
どこかピュアでまっすぐでよかったです。
めちゃめちゃ台詞噛んでましたけどねー。
天野小夜子(ベニータ)
ゴージャス、です。
演技は下手かなと思いましたが存在感があってよかった。
彼女は初演でもベニータを演じたそうです。
演出/宮本亜門
ReviewWriteDate:2000/7/11
LastUpdate:2000/7/11
Cast:木村佳乃(キャンディ)/増沢望(デヴィッド)/橋本さとし(バーニー)/笠原浩夫(ロバート)/明星真由美(ジェリィ)/平宮博重(ケイン)/天野小夜子(ベニータ)
Tokyo 2000.7.1~16 @パルコ劇場
Osaka 2000.7.19~23 @シアター・ドラマシティ
Date:2000/7/9 13:00 Y13
Note:
93年に宮本亜門の演出で上演され、内容の過激さでセンセーショナルな話題を呼んだ作品を、新キャストで再演する。(シアターガイドより)
ただし96年に脚本が改訂になっている為今回の公演は改訂版の上演となる。
※ベニータ役の天野小夜子のみ初演と同じ。
Story
新刊本の書評を書く仕事をしているキャンディは、ウェイターの元恋人のデヴィッドと同居中。ゲイであることを告白した彼と親友として同居しているのだ。そんなデヴィッドは友人で妻帯者のバーニーへ想いを寄せているが、バーニーはゲイではない。キャンディは拒食症に悩みつつも、バーテンのロバート、同じジムに通うレズビアン・ジェリィに言い寄られ、つきあい出す。そんな中、エドモントンの街に連続婦女暴行事件が発生する──
ヒトコトReview:
--------------------------------------------------------------------------------
主役は木村キャンディじゃない!! 増沢デヴィッド&橋本バーニーこそが主役也!
--------------------------------------------------------------------------------
えんぺで酷評されていたので多少構えて観劇してしまいました。
感想としてはすんなりと「あれ、おもしろいじゃん」です。
ただよくよくその「おもしろい」を掘り下げて見ると確かにおかしいのかもしれません。
わたしがおもしろいと感じたポイントをかいつまんで言うと
・なんといっても増沢デヴィッド&橋本バーニー!!
・なんとなく感じさせられるどうしようもない閉塞感
てことなんです。
上記ヒット項目の解説はあとにまわすとして、先に?の部分から。
■悲しいかな、主人公キャンディに共感できない
どうしようもない女のイヤな部分を描いているわけだから、
同性であるわたしは自分を見ているようでもちろんイヤになるのは当たり前なのですが、
「ああわたしもこんなヤナ奴だよ。だからキャンディがそうしちゃうのわかるよ」
ていう思いは湧き起こりませんでした。(これを共感と呼ぶと思う)
「この子は理解できん。この子はおかしい!」
て思ってしまいました。
それが脚本と演出の狙いだったなら、ずばり引っかかっています。
でも多分、それは狙いじゃないですよね?
わたしの狭量な発想かもしれないけれど
「キャンディはこんなにデヴィッドが好きなのに報われない
(とパンフにあるからそうなんだろう。ちっともそんな感じはしなかったけど。甘い伏線はあるけどさ)。
だから拒食症にもなるし(これも頭の伏線のみだから忘れそう。ピザ食ってるぞ! て思いませんでした? まあパンフには拒食症が肩書なんでそうなんでしょう)
そんなに好きじゃない人とでも関係を持ちたいんだ。わかるよ、わかる!」
て共感させないといけないんだと思うのです、とりあえず女性の観客は。
もしかしたらわたしが模範的女性観客じゃないのでしょうか?
ただ、キャンディの描き方がちょっと全編通して甘かったような。
デヴィッド&バーニー(異端・異常)に対するキャンディ(普通)なのはわかるのですがなんとも中途ハンパに存在してしまっていました。
そもそも3人がキーの物語なのに、宣伝が木村佳乃中心だからダントツの主人公だと思って見に行くわけじゃないですか。
で、結局主人公にはなりえてなかったと思うので。
途中からうまく舞台がノって来たのでキャンディが生きてはきましたが
まあ元気なねーちゃんという意味でしかなかった。
木村嬢の演技は悪くはなかったです。
ただガツンと来るこないが役柄の問題なのか演技の問題なのかは
見当がつきませんので言及は避けます。
もし「ただただ普通のイヤなところをもった女の子」
という役を描きたかったのなら正解なのだと思います。伝わりにくいですが。
キャンディが伝わらないので
キャンディを介して伝わるべくデヴィッド&バーニーが突出してしまい
わたしの目はもうその2人だけにくぎ付けでした。
あと、バーニーの奇怪な行動の意味理由っていうのが
わかるようでわからない。
わかると感じる部分は橋本バーニーの力であって、
脚本を読んだだけだと首をひねっていたかもしれないです。
ただまあ、役者が存在してはじめて演劇だと思うのでそれでよいのかもしれませんが。
ところでキャンディの友達で自殺をしてしまった子って
キャンディにとって何だったんでしょうね?(まあ友達なのはわかりますが)
彼女の死にあれだけ反応を示しながら
その死によっては何の影響も受けていないようなキャンディ。
(叫ぶ・独白の部分はあからさまにわかりますが)
やっぱり曖昧模糊としたままです・・・
■休憩時間の入り方が切ない・・・
どうしても気になったこと。
おそらく会場の全員が思ったと思うのですが、休憩時間。
たしかに長いお芝居ではありましたが「どうしてここで!?」というシーンでした。
盛り上がりがそこで分断されてしまうのです。
で、盛り上がって叫んでいたキャストが
ちょっとは暗いが肉眼でばっちり見える舞台上を
てくてく消えてゆくのです。
あああああ、なんてことでしょう。
せめて完全な暗転にしてキャスト去らせてから休憩にしてほしかったです。
■増沢デヴィッド&橋本バーニー、素敵!!!
というか、わたし個人はもう橋本バーニーしか見ていなかった。
とにかく目を惹く圧倒的な存在感。
パルコ劇場って決して小さな箱ではないと思うのですが
めらめら気を感じました。
まあ席が近いからかもしれませんが。
ちょっとした所作等、目をひきます。
そのバーニーの相手役である増沢デヴィッドは
「滅茶苦茶やっててイヤなヤツ」をうまいこと伝えた上で
「でもとてもナイーヴ」と攻めてくるので、勝てっこありません。
ふたりが建物の上の方で語り合うシーン、絶妙です。
デヴィッドのバーニーへの思いは愛というか恋なんだけれども
バーニーのそれがはっきりわからないまでも
デヴィッドの存在が簡単なものでないことは痛いほど伝わります。
■どこまでも続く閉塞感
パンフにもあったのですが、初演の1993年より今の時代の方が閉塞感に満ちていると思います。
だからでしょうか? この
「どこにも出ていけない、どこにも出ていかない」
澱んだ空気が、否定するより先に根っこにひっかかって納得させられてしまう。
凶悪事件だったりセクシャリティの問題だったり色々とあるとは思いますが
それ以上にどうにかしたいという思いがあっても
その思いがパワーには結びつかなくてただ「そこにいる」ていう感じが
「今のわたし」には心地よかったです。
■各キャストへの感想
木村佳乃(キャンディ)
上記の通りです。でも身体ほそいね、きれいだねー。
わりに顔がおおきくて驚きました。
増沢望(デヴィッド)
わがままで切なくてナイーヴで放っておけない彼。
観客であるわたしもすっかり彼に翻弄されてしまいました。
ふーん、俳優座なんだ。
橋本さとし(バーニー)
元・新感線、だそうです。
今まで彼のことを知らなかったのが恥ずかしい。テレビも見ないしなあ。
わたしにとってのこの公演はイコール橋本さとしLOVE!です。
わきに立っているだけでも目をそらせませんでした。
笠原浩夫(ロバート)
スタジオライフ所属の花形。
今回はスタジオライフの笠原さん分優先予約でチケットを取りました。
女性とからんでいる笠原さん、はじめてみました。
やっぱり長身だと得ですね、舞台映えします。
初の外部出演でしたが、まあいつも通りナイーヴな彼でした。
明星真由美(ジェリィ)
NODAMAP農業少女出るんですね。
すっかりキャンディが食われていましたが、まあそういう役なのかもしれません。
平宮博重(ケイン) →のちの成宮寛貴である(笑)
この公演の為のオーディションで選ばれた彼。
いきなり変なことまでさせられてちょっと可哀想。役者って大変だね(笑)。
どこかピュアでまっすぐでよかったです。
めちゃめちゃ台詞噛んでましたけどねー。
天野小夜子(ベニータ)
ゴージャス、です。
演技は下手かなと思いましたが存在感があってよかった。
彼女は初演でもベニータを演じたそうです。
作/アレキサンドル・デュマ
訳/宗 左近
出版社/創元推理文庫
ReviewWriteDate:2000/7/11
LastUpdate:2000/8/15
Note:
アランドロンの同名映画とは別物です。
Story:
風車小屋とチューリップの国オランダ、その片隅で神秘の花、黒いチューリップの創造に没頭する青年コルネリウスは陰謀にまきこまれて、いまは断頭台へひかれて行く運命に在った。彼を救わんとする、けなげな牢番の娘ローザの必至の活躍。神秘の花ひらく運命の時は、刻一刻と迫ってきた。オランダ戦争の史実を背景に、大自然の摂理の妙と地上の血なまぐさい係争を背景に展開する、大デュマ会心の恋と戦乱の雄渾なる一大事叙事詩!
(口絵より)
──ということですが。
ヒトコトReview:
--------------------------------------------------------------------------------
黒いチューリップはまさに現代らしいコメディである!!!
--------------------------------------------------------------------------------
そもそもこの本を読んだ理由というのは今年の夏にある
スタジオライフの公演演目だから。
基本的にわたしは「予習してゆく人」なので・・・
それにしても上↑の解説読んで本買った人だったら、多分怒っているよ。(笑)
ものは言いようというか、まあすごい解説です。
もちろん、おもしろくなかったわけではありません。
ある意味、めちゃめちゃ面白かったです。つっこみの声がとまりません。
これがデュマの罠なのかしら?
それともとんでもない訳文で責めたてる宗氏の陰謀?
(初版が1971年とのこと、それにしても訳が・・・)
■訳文を堪能あれ!
なぜコメディなのか?
オランダの有力者である兄弟が平気で
「お兄さん、お痛みになるんでしょう?」
「きみにあえたんだから、もう痛みはしませんよ、ジャン」
(中略)
「でも、きみがここにいるんだもの、もうなにもかも忘れようね」
とか妙な口調で会話すること事体で、もう訳者の罠にはまっているに違いない。(笑)
いったい原文ではどんな感じなのでしょう?
いたるところがこんな文章でうめ尽くされたこの本、
ページ数は多いですがそういったどうでもいい? 描写にうめ尽くされているだけで
内容だけ追うなら絶対半分のページ数でいいはず。
それでもついつい読んでしまう文。罠かもしれない──
■ヒロイン・ローザこそが救世主──王子と姫の逆転現象
そして一番のコメディ要素は、ヒロインの強さ、ヒーローの情けなさ。
ヒーローであるはずのコルネリウスはチューリップマニア。
かわいい彼女よりチューリップのことばっかり考えています。
途中「チューリップよりローザの方が大切だと気づいた」みたいなくだりがありますが
そうはいいつつも
しかし、ローザはなぜチューリップについて語るのを禁じたのだろうか。
それがローザの持つ重大な欠陥だった。
コルネリウスが溜息をつきながら心に思ったのは、
女性というものは完全でありえないのだということであった。
なんて馬鹿なことを考えているあたり、根っからのチューリップマニアの改心度合いは甘い。
対するローザはチューリップのことばかり考えている彼に嫉妬しつつも
彼のためにチューリップに関する知識を得て彼のかわりに黒いチューリップを栽培します。
途中、黒いチューリップを奪われた後のローザは完全に主人公です。
チューリップを追って国を横断してオレンジ公ウィリアム(うーん、サラディナーサだ)に直訴して
みごと大団円に持ちこむのです。
ヒーロー、コルネリウスは350ページに渡るこの本のほとんどを牢獄で過ごし、
自力で何をなすわけでもなく、嘆くか待っているだけで
途中ちょっとだけ人を殴ってみますが、ストーリー上ちょっと暴れてみたという感じ。
やっていることと言えば女の子を恋しく思ってやつれたり、チューリップを思ってやつれたり(×100回)。
対してヒロインは歴史的な人物相手に渡り合って幸せを勝ち取る。
結局、ヒロインによってヒーローは黒いチューリップの栄光も取り戻せたし、
牢獄からも解放されるのです。
自分で花嫁衣裳着て待ってるんだから、こいつは大物です。(オレンジ公に言われたからって)
ここではまぎれもなく、王子と姫の逆転現象が起こっています。
まさに現代らしい──
お姫様は気が弱くて外に出られないナイーヴな王子様の為に、
いばらを切り抜けて助けてきてくれるわけです。
なんとも情けなくも「いるいるこういうやつ!」というコルネリウスを
どうやって芝居にするつもりなんだろう、スタジオライフ?
これはもう、耽美じゃなくてコメディでつくるしかないでしょ──?
訳/宗 左近
出版社/創元推理文庫
ReviewWriteDate:2000/7/11
LastUpdate:2000/8/15
Note:
アランドロンの同名映画とは別物です。
Story:
風車小屋とチューリップの国オランダ、その片隅で神秘の花、黒いチューリップの創造に没頭する青年コルネリウスは陰謀にまきこまれて、いまは断頭台へひかれて行く運命に在った。彼を救わんとする、けなげな牢番の娘ローザの必至の活躍。神秘の花ひらく運命の時は、刻一刻と迫ってきた。オランダ戦争の史実を背景に、大自然の摂理の妙と地上の血なまぐさい係争を背景に展開する、大デュマ会心の恋と戦乱の雄渾なる一大事叙事詩!
(口絵より)
──ということですが。
ヒトコトReview:
--------------------------------------------------------------------------------
黒いチューリップはまさに現代らしいコメディである!!!
--------------------------------------------------------------------------------
そもそもこの本を読んだ理由というのは今年の夏にある
スタジオライフの公演演目だから。
基本的にわたしは「予習してゆく人」なので・・・
それにしても上↑の解説読んで本買った人だったら、多分怒っているよ。(笑)
ものは言いようというか、まあすごい解説です。
もちろん、おもしろくなかったわけではありません。
ある意味、めちゃめちゃ面白かったです。つっこみの声がとまりません。
これがデュマの罠なのかしら?
それともとんでもない訳文で責めたてる宗氏の陰謀?
(初版が1971年とのこと、それにしても訳が・・・)
■訳文を堪能あれ!
なぜコメディなのか?
オランダの有力者である兄弟が平気で
「お兄さん、お痛みになるんでしょう?」
「きみにあえたんだから、もう痛みはしませんよ、ジャン」
(中略)
「でも、きみがここにいるんだもの、もうなにもかも忘れようね」
とか妙な口調で会話すること事体で、もう訳者の罠にはまっているに違いない。(笑)
いったい原文ではどんな感じなのでしょう?
いたるところがこんな文章でうめ尽くされたこの本、
ページ数は多いですがそういったどうでもいい? 描写にうめ尽くされているだけで
内容だけ追うなら絶対半分のページ数でいいはず。
それでもついつい読んでしまう文。罠かもしれない──
■ヒロイン・ローザこそが救世主──王子と姫の逆転現象
そして一番のコメディ要素は、ヒロインの強さ、ヒーローの情けなさ。
ヒーローであるはずのコルネリウスはチューリップマニア。
かわいい彼女よりチューリップのことばっかり考えています。
途中「チューリップよりローザの方が大切だと気づいた」みたいなくだりがありますが
そうはいいつつも
しかし、ローザはなぜチューリップについて語るのを禁じたのだろうか。
それがローザの持つ重大な欠陥だった。
コルネリウスが溜息をつきながら心に思ったのは、
女性というものは完全でありえないのだということであった。
なんて馬鹿なことを考えているあたり、根っからのチューリップマニアの改心度合いは甘い。
対するローザはチューリップのことばかり考えている彼に嫉妬しつつも
彼のためにチューリップに関する知識を得て彼のかわりに黒いチューリップを栽培します。
途中、黒いチューリップを奪われた後のローザは完全に主人公です。
チューリップを追って国を横断してオレンジ公ウィリアム(うーん、サラディナーサだ)に直訴して
みごと大団円に持ちこむのです。
ヒーロー、コルネリウスは350ページに渡るこの本のほとんどを牢獄で過ごし、
自力で何をなすわけでもなく、嘆くか待っているだけで
途中ちょっとだけ人を殴ってみますが、ストーリー上ちょっと暴れてみたという感じ。
やっていることと言えば女の子を恋しく思ってやつれたり、チューリップを思ってやつれたり(×100回)。
対してヒロインは歴史的な人物相手に渡り合って幸せを勝ち取る。
結局、ヒロインによってヒーローは黒いチューリップの栄光も取り戻せたし、
牢獄からも解放されるのです。
自分で花嫁衣裳着て待ってるんだから、こいつは大物です。(オレンジ公に言われたからって)
ここではまぎれもなく、王子と姫の逆転現象が起こっています。
まさに現代らしい──
お姫様は気が弱くて外に出られないナイーヴな王子様の為に、
いばらを切り抜けて助けてきてくれるわけです。
なんとも情けなくも「いるいるこういうやつ!」というコルネリウスを
どうやって芝居にするつもりなんだろう、スタジオライフ?
これはもう、耽美じゃなくてコメディでつくるしかないでしょ──?
<<
前のページ
カレンダー
| 03 | 2025/04 | 05 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
カテゴリー
最新CM
[03/19 秘書アズアズ]
[01/06 通りすがり]
[01/05 Hiroic]
[01/05 通りすがり]
[11/26 Hiroic]
最新記事
(11/16)
(11/07)
(11/01)
(10/26)
(10/26)
(09/11)
(07/06)
(06/29)
(02/17)
(02/17)
(02/17)
(06/24)
(05/28)
(04/20)
(04/01)
(01/08)
(10/11)
(08/29)
(08/24)
(07/30)
最新TB
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(07/11)
(07/11)
(07/17)
(07/17)
(07/20)
(07/20)
(08/08)
(08/15)
(08/15)
(08/19)
(08/20)
(08/26)
(08/26)
(09/04)
(09/30)
(10/01)
(10/01)
(10/01)
(10/01)
(10/07)
忍者アナライズ
リンク
プロフィール
HN:
ひろいっく
性別:
非公開