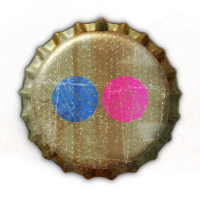作/パウロ・コエーリョ
訳/山川紘矢+山川亜希子
出版社/角川文庫
ReviewWriteDate:2000/7/17
LastUpdate:2000/7/17
Notes:
作者、パウロ・コエーリョはブラジル人。作品はスペイン語で書かれている。
『星の巡礼』(角川文庫)で有名。だそうです。
Stoy:
スペインの小さな田舎街で教鞭を執る29歳のピラールは、12年ぶりに再会した幼なじみの男性から愛を告白される。病を治す力をもつ修道士の彼は、彼女に自分と一緒に来てほしいという。今の暮らしを捨てる決心がつかずに悩むピラールだったが、彼との旅を通して真実の愛と神の力を再発見してゆく……。
(帯より)
ヒトコトReview:
--------------------------------------------------------------------------------
キリスト教的背景と普遍的な想いとの交差。バランスは難しい……
--------------------------------------------------------------------------------
■圧倒的な冒頭、これだけで実は満足です
小説の冒頭(はしがき除く)、すばらしい文章です。
実はタイトル買いしてしまったこの本ですが、この文章が読めただけでとりあえず満足。
少し長いですが引用・・・
訳者さま、ありがとう。
こんなにきれいに訳していただいて。これがなかったらこの本はずっと難解になっていたと思う。
冒頭でぐいとこの「想い」を脳裏に焼き付けてくれたからこそ
その後の謎な思いにも耐えられたといいますか──。
■キリスト教(宗教)と小説
これは修道士の「彼」と主人公ピラールのお話。
この本はどうしてもこの宗教観から逃げることは出来ません。
はしがきで著者が
「神は形式のもとにいるのではなく、祈るもの次第でどこにでもいる。宗教は形ではない」
といった意のことを言っているのですが
まさしくそれはその通りだと共感することができるのですが
やはり全体を通して宗教を背負っていないわたし(というか多くの日本人)には
どうにもなじめない話題では在りました。
言いたい意味、思いは言葉として伝わるのに、リアリティと実感がともなわないのは
バックボーンの問題なのでしょう。
神=男性ではなく神=女性・母性・マリアという転換は
背景に信仰もしくは信仰を持っていた過去があればもっとぐっと内面をえぐるもののはずなのに
どうにもさらっと読んでしまいました。
だからピラールの中で信仰が戻って来ると言われてもピンと来ない。
恐らくストーリーを推し進めるキーであるはずなのに。
こう考えると小説だとか映画だとかそういった創作物というのは
否応無しにそのバックボーンを背負って、必ず縛りを持って、対象としたある一定の人間により訴えるものでしかないのですね。
より普遍的な話題になれば別なんでしょうし、もっとすごい才能からすれば打ち破るのは可能なのかもしれない。
ただ、やはりそれには限界があって、どっかで「誰々向け」「何々向け」担ってしまうんじゃないでしょうか。
そういったジャンル分け嫌いなんですが、それも有りなのかな、としみじみ思いました。
特に一般的な日本人にとっての、神様っていうのは信仰しつづけるもの、というよりは
つねにそこに「いて」たまに悪戯さえしかけてくる八百万の神みたいなベースがあるように思います。
だからキリスト教的な信仰からは自然遠くなってしまうんでしょうね。
(あくまで私の主観です)
あと「愛」という言葉の捕らえ方も、もしかしたら微妙なのかも、と思いました。
■『他者』と自分の境界線
話の骨子はこの
「宗教・祈りは形式ではない=修道院にいることでも戒律をまもることでもない」
というのと
「危険を冒すことを恐れては人生は変わらない。自分を抑制している『他者』を自分から追い出して、『魔法の瞬間』を見逃さないよう正しく生きて行く」
ということなのですが
後者に関しては身につまされました。
自分がこの『他者』の存在を知っているから。
途中ピラールが「どうしてわたしはこんなに頑張って自分がなりたくないものになろうと努力してきたのだろう」と思うくだりがあるのですが、わたしも振り返ればそんな日々です。
日本語としてあまりすんなりと意識に入ってきにくい『他者』ですが──はて原文ではこの『他者』というのはどういう単語で表現されているのでしょう? ──意味、意義、思いは伝わってきました。
明日から自分が変わることはないですが。
というか、もちろんそんなこと大昔から自覚済ですので…とするとわたしは大変ずるいんでしょうねえ。(笑)
■ネタばれですが──「彼」とピラールの想い
ちょっと驚いたのは、ネタ。
マリアの声を聞き奇跡を起こせる修道士の「彼」は
「愛する幼馴染とのひとりの人間としての生活」と「伝統的宗教生活」との間で迷い、
決断をするためにピラールと再会していたのでした。
おいおい、そりゃないだろー、とピラール弁護のわたし。
でも、人なら「もしかしたらそうなったかもしれない自分」に賭けてみたくなるのかも知れません。
結果、伝統的宗教生活にとらわれるよりピラールへの愛を優先させた「彼」は
奇跡もマリアの声も手放してピラールの元に戻っているわけです──。
いや、上のネタには正直フイをつかれました。
迷いながら、だからこそ自分試すために女に会いに来るとは──と。
ピラールがマジで「彼」に惚れても自分にとっては宗教生活が大切だったら
嵐だけまきおこしてとっとと修道院に戻るつもりだったのね、あんた!
さすが男性作者、女のわたしじゃ思いもつきませんでした。
女の読者なんてものは自分がこうされたいという理想像を求めて読んでいるので
「女」がそんな踏絵にされるなんて思わずに読んでいるわけですから。
女性が自分を試すために男性に会いに行くなら平然と読んでたと思います。
ああ感動──なはずなんですが。
実はわたし、本を半分ほど読むまで気づきませでした。
「彼」は「彼」でしかなくて、名前、ないんですね──。
というかこの小説では名前が出てこない。
のっぺらぼうの、「彼」。
さてこれはお話の問題なのでしょうか?
それとも訳文の問題?
正直、この「彼」がピラールを愛しているっていうのは本当に文字通りだけで
想いがともなっていない小説上の設定っていう気がする。
「彼」には個性もなんも、感じられないのです。
だからそんな「彼」を愛するようになるピラールの想いも説得力がない。
いったい魅力は何なんだね?
それは主に宗教的瞬間を分かち合うことで進んでいるように見えるので
やはり宗教観の乏しいわたしには理解できないのか?
ただ、どうも小説としてきっちりと描くべき「人」がないままに話が進んで行くので
結局よくわかならい──という結果になっているような気がします。
先に「他者に関する記述が思い当たった」と書きましたが
文章を読んで文章から自分はそう読み取ることで思い当たりましたが、
「おうおう、そうなんだよー」という感情論で言うならば、小説になっていない気がします、他者の逸話。
これは宗教観をともなったヒーリング本なんだって言いきってしまえばこれでもいいんでしょうが
小説にはなりえてないな、というのが実感です。
話し言葉もモンキリだから、誰がしゃべってんだかさっぱりわからないし。
それにしてもこういう外国文学の主人公の女性って
どうしていつも同じなのかなー?
多分、間違いなく訳文なんだろうな──なんて、思いました。
ただまあ、あとで読み返すと「変わる」かもしれないお話では有ります。
その人のその時のコンディションによって、想いが変わるような、そういった奥深さは感じました。
しばらくしたらまた読んでみよっと。
訳/山川紘矢+山川亜希子
出版社/角川文庫
ReviewWriteDate:2000/7/17
LastUpdate:2000/7/17
Notes:
作者、パウロ・コエーリョはブラジル人。作品はスペイン語で書かれている。
『星の巡礼』(角川文庫)で有名。だそうです。
Stoy:
スペインの小さな田舎街で教鞭を執る29歳のピラールは、12年ぶりに再会した幼なじみの男性から愛を告白される。病を治す力をもつ修道士の彼は、彼女に自分と一緒に来てほしいという。今の暮らしを捨てる決心がつかずに悩むピラールだったが、彼との旅を通して真実の愛と神の力を再発見してゆく……。
(帯より)
ヒトコトReview:
--------------------------------------------------------------------------------
キリスト教的背景と普遍的な想いとの交差。バランスは難しい……
--------------------------------------------------------------------------------
■圧倒的な冒頭、これだけで実は満足です
小説の冒頭(はしがき除く)、すばらしい文章です。
実はタイトル買いしてしまったこの本ですが、この文章が読めただけでとりあえず満足。
少し長いですが引用・・・
ピエドラ川のほとりで私は泣いた。この川の水の中に落ちたのもは、木の葉も虫も、鳥の羽さえも、岩に姿を変えて、川底に沈むと言い伝えられている。心を胸の中から取り出して、流れの中に投げ込めるものならば、恋もこの苦しみも終わって、私はすべてを忘れることができるだろうに。
ピエドラ川のほとりにすわって、私は泣いた。冬の空気がわたしのほおの涙を冷し、その冷たい涙は、目の前の流れの中へはらはらと落ちて行った。この川はどこかでもう一つの川と合流し、さらにまた、別の川と合流して、私の心からも視野からもずっと離れたところで、海と一つになるのだ。
私の涙もまた、ずっと遠くまで流れてゆきますように。そして私が、かつて彼を思って泣いたことを、私の愛が思い出しませんように。
訳者さま、ありがとう。
こんなにきれいに訳していただいて。これがなかったらこの本はずっと難解になっていたと思う。
冒頭でぐいとこの「想い」を脳裏に焼き付けてくれたからこそ
その後の謎な思いにも耐えられたといいますか──。
■キリスト教(宗教)と小説
これは修道士の「彼」と主人公ピラールのお話。
この本はどうしてもこの宗教観から逃げることは出来ません。
はしがきで著者が
「神は形式のもとにいるのではなく、祈るもの次第でどこにでもいる。宗教は形ではない」
といった意のことを言っているのですが
まさしくそれはその通りだと共感することができるのですが
やはり全体を通して宗教を背負っていないわたし(というか多くの日本人)には
どうにもなじめない話題では在りました。
言いたい意味、思いは言葉として伝わるのに、リアリティと実感がともなわないのは
バックボーンの問題なのでしょう。
神=男性ではなく神=女性・母性・マリアという転換は
背景に信仰もしくは信仰を持っていた過去があればもっとぐっと内面をえぐるもののはずなのに
どうにもさらっと読んでしまいました。
だからピラールの中で信仰が戻って来ると言われてもピンと来ない。
恐らくストーリーを推し進めるキーであるはずなのに。
こう考えると小説だとか映画だとかそういった創作物というのは
否応無しにそのバックボーンを背負って、必ず縛りを持って、対象としたある一定の人間により訴えるものでしかないのですね。
より普遍的な話題になれば別なんでしょうし、もっとすごい才能からすれば打ち破るのは可能なのかもしれない。
ただ、やはりそれには限界があって、どっかで「誰々向け」「何々向け」担ってしまうんじゃないでしょうか。
そういったジャンル分け嫌いなんですが、それも有りなのかな、としみじみ思いました。
特に一般的な日本人にとっての、神様っていうのは信仰しつづけるもの、というよりは
つねにそこに「いて」たまに悪戯さえしかけてくる八百万の神みたいなベースがあるように思います。
だからキリスト教的な信仰からは自然遠くなってしまうんでしょうね。
(あくまで私の主観です)
あと「愛」という言葉の捕らえ方も、もしかしたら微妙なのかも、と思いました。
■『他者』と自分の境界線
話の骨子はこの
「宗教・祈りは形式ではない=修道院にいることでも戒律をまもることでもない」
というのと
「危険を冒すことを恐れては人生は変わらない。自分を抑制している『他者』を自分から追い出して、『魔法の瞬間』を見逃さないよう正しく生きて行く」
ということなのですが
後者に関しては身につまされました。
自分がこの『他者』の存在を知っているから。
途中ピラールが「どうしてわたしはこんなに頑張って自分がなりたくないものになろうと努力してきたのだろう」と思うくだりがあるのですが、わたしも振り返ればそんな日々です。
日本語としてあまりすんなりと意識に入ってきにくい『他者』ですが──はて原文ではこの『他者』というのはどういう単語で表現されているのでしょう? ──意味、意義、思いは伝わってきました。
明日から自分が変わることはないですが。
というか、もちろんそんなこと大昔から自覚済ですので…とするとわたしは大変ずるいんでしょうねえ。(笑)
■ネタばれですが──「彼」とピラールの想い
ちょっと驚いたのは、ネタ。
マリアの声を聞き奇跡を起こせる修道士の「彼」は
「愛する幼馴染とのひとりの人間としての生活」と「伝統的宗教生活」との間で迷い、
決断をするためにピラールと再会していたのでした。
おいおい、そりゃないだろー、とピラール弁護のわたし。
でも、人なら「もしかしたらそうなったかもしれない自分」に賭けてみたくなるのかも知れません。
結果、伝統的宗教生活にとらわれるよりピラールへの愛を優先させた「彼」は
奇跡もマリアの声も手放してピラールの元に戻っているわけです──。
いや、上のネタには正直フイをつかれました。
迷いながら、だからこそ自分試すために女に会いに来るとは──と。
ピラールがマジで「彼」に惚れても自分にとっては宗教生活が大切だったら
嵐だけまきおこしてとっとと修道院に戻るつもりだったのね、あんた!
さすが男性作者、女のわたしじゃ思いもつきませんでした。
女の読者なんてものは自分がこうされたいという理想像を求めて読んでいるので
「女」がそんな踏絵にされるなんて思わずに読んでいるわけですから。
女性が自分を試すために男性に会いに行くなら平然と読んでたと思います。
ああ感動──なはずなんですが。
実はわたし、本を半分ほど読むまで気づきませでした。
「彼」は「彼」でしかなくて、名前、ないんですね──。
というかこの小説では名前が出てこない。
のっぺらぼうの、「彼」。
さてこれはお話の問題なのでしょうか?
それとも訳文の問題?
正直、この「彼」がピラールを愛しているっていうのは本当に文字通りだけで
想いがともなっていない小説上の設定っていう気がする。
「彼」には個性もなんも、感じられないのです。
だからそんな「彼」を愛するようになるピラールの想いも説得力がない。
いったい魅力は何なんだね?
それは主に宗教的瞬間を分かち合うことで進んでいるように見えるので
やはり宗教観の乏しいわたしには理解できないのか?
ただ、どうも小説としてきっちりと描くべき「人」がないままに話が進んで行くので
結局よくわかならい──という結果になっているような気がします。
先に「他者に関する記述が思い当たった」と書きましたが
文章を読んで文章から自分はそう読み取ることで思い当たりましたが、
「おうおう、そうなんだよー」という感情論で言うならば、小説になっていない気がします、他者の逸話。
これは宗教観をともなったヒーリング本なんだって言いきってしまえばこれでもいいんでしょうが
小説にはなりえてないな、というのが実感です。
話し言葉もモンキリだから、誰がしゃべってんだかさっぱりわからないし。
それにしてもこういう外国文学の主人公の女性って
どうしていつも同じなのかなー?
多分、間違いなく訳文なんだろうな──なんて、思いました。
ただまあ、あとで読み返すと「変わる」かもしれないお話では有ります。
その人のその時のコンディションによって、想いが変わるような、そういった奥深さは感じました。
しばらくしたらまた読んでみよっと。
PR
Comment
コメントの修正にはpasswordが必要です。任意の英数字を入力して下さい。
カレンダー
| 03 | 2025/04 | 05 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
カテゴリー
最新CM
[03/19 秘書アズアズ]
[01/06 通りすがり]
[01/05 Hiroic]
[01/05 通りすがり]
[11/26 Hiroic]
最新記事
(11/16)
(11/07)
(11/01)
(10/26)
(10/26)
(09/11)
(07/06)
(06/29)
(02/17)
(02/17)
(02/17)
(06/24)
(05/28)
(04/20)
(04/01)
(01/08)
(10/11)
(08/29)
(08/24)
(07/30)
最新TB
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(07/11)
(07/11)
(07/17)
(07/17)
(07/20)
(07/20)
(08/08)
(08/15)
(08/15)
(08/19)
(08/20)
(08/26)
(08/26)
(09/04)
(09/30)
(10/01)
(10/01)
(10/01)
(10/01)
(10/07)
忍者アナライズ
リンク
プロフィール
HN:
ひろいっく
性別:
非公開